少子化の流れの中で、2歳の拡大では有権者は余り変わらないものと思うが、これから1年間を使って高校等の場で選挙に対する意識を高めて、投票することを通じて責任有る市民である義務を果たす大人に成って貰いたいと願うところである。
さて、今議会で田中議員が配付した資料に今回の統一地方選挙における年齢別の有権者数と投票者数が示されていた。これは県からの指示で選挙管理委員会事務局が木更津中央公民館投票区(第6投票区)の投票状況を調べたもので、作業は職員が手作業で数え上げるという気の遠くなる作業である。従って、他の投票区での調査が行われていないので、市全体を代表しているとは断言できないが、傾向に大きな違いがないとすると憂慮すべき点が多い。まずは4月12日の県議会議員選挙と26日の市議会議員選挙の有権者及び投票者・投票率のデータを掲載する。
| 県議会議員選挙 (4/12) | ||||||
| 年齢 | 有権者数 | 投票者数 | 投票者率(%) | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 20〜24 | 45 | 60 | 6 | 17 | 13.33 | 28.33 |
| 25〜29 | 58 | 63 | 15 | 18 | 25.86 | 28.57 |
| 30〜34 | 87 | 57 | 28 | 20 | 32.18 | 35.09 |
| 35〜39 | 79 | 67 | 32 | 29 | 40.51 | 43.28 |
| 40〜44 | 108 | 94 | 35 | 43 | 32.41 | 45.74 |
| 45〜49 | 88 | 72 | 42 | 38 | 47.73 | 52.78 |
| 50〜54 | 96 | 88 | 52 | 47 | 54.17 | 53.41 |
| 55〜59 | 90 | 76 | 60 | 48 | 66.67 | 63.16 |
| 60〜64 | 94 | 87 | 59 | 51 | 62.77 | 58.62 |
| 65〜69 | 95 | 102 | 51 | 66 | 53.68 | 64.71 |
| 70〜74 | 83 | 103 | 49 | 67 | 59.04 | 65.05 |
| 75〜79 | 59 | 86 | 33 | 47 | 55.93 | 54.65 |
| 80〜84 | 45 | 71 | 25 | 34 | 55.56 | 47.89 |
| 85〜 | 26 | 93 | 9 | 33 | 34.62 | 35.48 |
| 合計 | 1,053 | 1,119 | 496 | 558 | 47.10 | 49.87 |
| 市会議員選挙 (4/26) | ||||||
| 年齢 | 有権者数 | 投票者数 | 投票者率(%) | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 20〜24 | 44 | 59 | 11 | 16 | 25.00 | 27.12 |
| 25〜29 | 57 | 63 | 18 | 19 | 31.58 | 30.16 |
| 30〜34 | 85 | 57 | 27 | 18 | 31.76 | 31.58 |
| 35〜39 | 79 | 67 | 29 | 30 | 36.71 | 44.78 |
| 40〜44 | 108 | 93 | 38 | 48 | 35.19 | 51.61 |
| 45〜49 | 90 | 74 | 50 | 37 | 55.56 | 50.00 |
| 50〜54 | 94 | 85 | 55 | 58 | 58.51 | 68.24 |
| 55〜59 | 88 | 77 | 55 | 50 | 62.50 | 64.94 |
| 60〜64 | 95 | 86 | 67 | 62 | 70.53 | 72.09 |
| 65〜69 | 96 | 102 | 63 | 73 | 65.63 | 71.57 |
| 70〜74 | 80 | 103 | 56 | 79 | 70.00 | 76.70 |
| 75〜79 | 60 | 85 | 42 | 55 | 70.00 | 64.71 |
| 80〜84 | 46 | 70 | 30 | 40 | 65.22 | 57.14 |
| 85〜 | 26 | 94 | 9 | 44 | 34.62 | 46.81 |
| 合計 | 1,048 | 1,115 | 550 | 629 | 52.48 | 56.41 |
上記の表をグラフにすると下図のようになる。
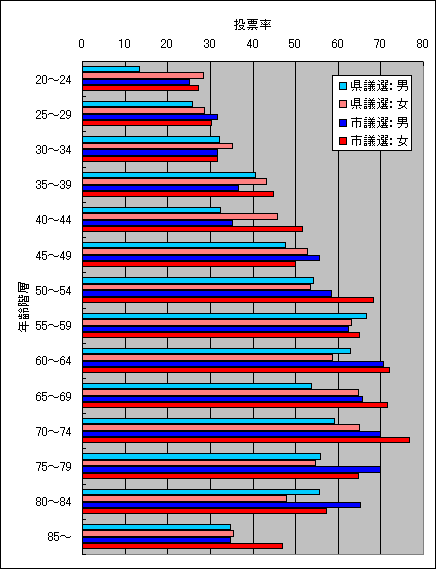
85歳以上の高齢者の投票率が低いのは、健康上の問題として投票所まで足を運べない方が多くなるからだろうと思われる。在宅投票などの制度も様々に考えて行かねばならないとは思うが、認知症が進んでいる高齢者に投票を強要する事が正しいことなのかは悩ましい話である。
話を若年層の政治参加に戻す。
世界に目を広げると多くの国で学生が世の中を変えようと頑張っている。最近では台湾で中国との交流を巡り国会に相当する立法院を占拠した「ひまわり運動」や香港で行政長官選挙制度を巡って街中で座り込みが続いた「雨傘運動」等が記憶に新しい。日本でも東日本大震災の後に反原発の動きも若干見られたが、激しい動きには繋がらず、多くの学生は政治に無関心であったように私には見えた。
大きな不満が出ないほど素晴らしい行政運営がされているなら理解できるが、学生達には卒業後の非正規労働やブラック企業と言われる問題が目前に迫っており、楽天的に過ごせるはずがないと思うのだが若年層の代弁者は現れ難い。怒れる国民の代表と信じた民主党の政権運営の未熟さを嫌になるほど見せつけられ、無気力になっているものとも思うが、これでよいのかと思う。
若者が荒れ回り、経済に影響を与えるような事態にならない我が国は、その分だけ治安等のコストを引き下げることが出来ると短期的的には喜べるのであるが、将来的にはエネルギッシュな外国の若者との競争に破れ国力の低下に繋がらないかと危惧もしているのだ。特定の思想に共感した教師に考え方を洗脳されるのも困りものであるが、無気力を打破するためには、我々政治の側に居るものが若者の世界に入って行かねばならないだろうと、今回の年齢引き下げの報道の中で考えていた。