厚生省の統計表によると速報値ながら昨年間は98万1千人に留まっており、私も一人の追加に協力してるが、人口減少が加速されていることを示す象徴的な数字である。因みに戦後となり統計が落ち着いた1947年以降の年別出生者数をグラフにしたものが下図である。
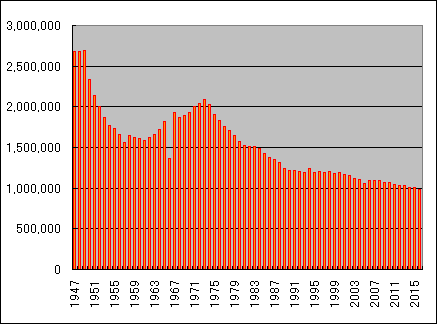
グラフを作成した数値は本頁の最後に添付する。
終戦後から1949年までのいわゆる「団塊の世代」の頃は毎年の出生数が260万人を越えており、それから考えると確かに著しい減少である。
当時は所得も低く行政による福祉施策が殆ど無い中で、明日をも知れない状況のもと、多くの子が産まれていたのである。それまでに続いた戦争で多くの命が失われた分を取り返そうとする勢いが有ったようにも思われる。
その後、1957年の約157万人まで減少するが、団塊Jrと言われる世代が増加し、1966年の丙午の特異値を除くと再び上昇し、1971年から1974年までは200万人を越え続ける。その世代が小学校に上がる頃、新日鐵の君津支出も伴い木更津でも学校が不足して多くの学校が増えていった。
団塊Jr世代の母親達は専業主婦も多く、会社勤務をする者の多くも結婚を機に「寿退職」と言われる慣行で会社を辞め、子育てを中心とした家事や年寄りの世話をこなし、子供が大きく成った頃にパートとして働きに出て、安い労働力を供給していた。その労働パターンには明確な男女差があり、社会的に問題視されていたが、保育園や高齢者福祉施設などが少なくて済んだことも彼女たちの無償労働のお陰であった。
一方、団塊Jrの女性達の多くは男女雇用均等法の時代を過ごし家庭に拘束されるような生き方を望まない者も多く、会社でのキャリアと結婚による退社を比較するようになり、更には結婚しても子育てで仕事を中断するリスクを避ける生き方も多く見られるようになった。特に都会の核家族では子供を預ける場所が無ければ働き続けることが出来ず、出産が敬遠された結果、東京都の出生率が全国最低の1.24(H28)に成っている状況である。
国による保育所の整備といった人口増加施策が遅れた原因は、団塊Jrの子供が次の山を作るのではという楽観があったものと私は思うが、そのようなピークを見ることもなく、グラフのように減少の一途を辿っているのである。
増田教授の本は何冊も読んでいるが、気になる論点がある。それは今後迎える高齢化社会で東京の膨大な高齢者の介護に地方から人材を吸収すると、地方では若者が不足し、東京では出生率が低いために、双方で人口減少を加速させてしまうため都会の高齢者を元気なうちに地方へ移住させ、そちらで介護を行うことで社会的な人口移動をくい止めるべきという点である。
これに添って生涯活躍のまち(日本版CCRC)構想というものが展開されているが、今まで何度も国土総合計画で進められ失敗してきた企業の地方移転という案が費えてしまったしまったように思うことだ。若い人や税収を納める企業を地方に展開しなくては効果が薄く思うのである。その延長に有った首都移転や道州制の話も最近はパッタリと聞かなくなっている。都心に住む官僚や大企業の幹部職員は都会の生活を満喫しながら、地方は地方で知恵を出せと言っているに等しく、国がテコ入れしている感覚はない。
個人的には人口減少社会も悪くないと考えており、10年も前に書いている事であるが、様々な日本にある資源を安定的に使えるチャンスになるのではとも考えている。急な減少は多くの痛みを伴うことも充分に理解しているが、そろそろ誰かその次の人口が減った後に訪れる明るい社会を示して希望を与え、子供を安心して残せるようにする事の方が健全ではないかと思いつつ、今回の記載を終える。
| 西暦 | 出生数 | 西暦 | 出生数 | 西暦 | 出生数 |
| 1947 | 2,678,792 | 1970 | 1,934,239 | 1993 | 1,188,282 |
| 1948 | 2,681,624 | 1971 | 2,000,973 | 1994 | 1,238,328 |
| 1949 | 2,696,638 | 1972 | 2,038,682 | 1995 | 1,187,064 |
| 1950 | 2,337,507 | 1973 | 2,091,983 | 1996 | 1,206,555 |
| 1951 | 2,137,689 | 1974 | 2,029,989 | 1997 | 1,191,665 |
| 1952 | 2,005,162 | 1975 | 1,901,440 | 1998 | 1,203,147 |
| 1953 | 1,868,040 | 1976 | 1,832,617 | 1999 | 1,177,669 |
| 1954 | 1,769,580 | 1977 | 1,755,100 | 2000 | 1,190,547 |
| 1955 | 1,730,692 | 1978 | 1,708,643 | 2001 | 1,170,662 |
| 1956 | 1,665,278 | 1979 | 1,642,580 | 2002 | 1,153,855 |
| 1957 | 1,566,713 | 1980 | 1,576,889 | 2003 | 1,123,610 |
| 1958 | 1,653,469 | 1981 | 1,529,455 | 2004 | 1,110,721 |
| 1959 | 1,626,088 | 1982 | 1,515,392 | 2005 | 1,062,530 |
| 1960 | 1,606,041 | 1983 | 1,508,687 | 2006 | 1,092,674 |
| 1961 | 1,589,372 | 1984 | 1,489,780 | 2007 | 1,089,818 |
| 1962 | 1,618,616 | 1985 | 1,431,577 | 2008 | 1,091,156 |
| 1963 | 1,659,521 | 1986 | 1,382,946 | 2009 | 1,070,035 |
| 1964 | 1,716,761 | 1987 | 1,346,658 | 2010 | 1,071,304 |
| 1965 | 1,823,697 | 1988 | 1,314,006 | 2011 | 1,050,806 |
| 1966 | 1,360,974 | 1989 | 1,246,802 | 2012 | 1,037,231 |
| 1967 | 1,935,647 | 1990 | 1,221,585 | 2013 | 1,029,816 |
| 1968 | 1,871,839 | 1991 | 1,223,245 | 2014 | 1,003,539 |
| 1969 | 1,889,815 | 1992 | 1,208,989 | 2015 | 1,005,677 |